【切土丁張】の掛け方|1:1.5「法面丁張」の計算方法・丁張板・杭の設置方法をわかりやすく解説
このブログでは、「切土法面丁張」の掛け方を解説しています。
法面丁張は「高低差」と「法勾配」から「水平距離」を求めて設置します。
土木では「丁張(ちょうはり)」といい、建築では「遣り方(やりかた)」といいます。
では、下の図のような掘削用の「切土丁張」を掛けてみましょう。

現場条件として
- 法勾配1:1.5(1割5分)
- 掘削計画高 FH=10.000m
- センターから法尻までの幅:「構造物=1.300m」+「作業スペース=0.500m」=1.800m
高低差と法勾配
切土丁張は、「掘削計画高」と「丁張の水平板(横板)」との「差(高低差)」を計算し、この高低差に「法勾配」を掛け算して「水平距離」を求めます。
土木の法勾配は、下の図のように呼びます。

高低差1.0mに対して、水平距離が0.5mや1.0mで呼び方が変わります。
幅杭の設置
- 最初にセンターからの「幅杭」を横断方向に2~3点ほど設置します。
幅杭を設置する位置は横断図を参考にして、切土開始ポイント(切出し)付近に設置します。
2点以上設置する理由は、丁張の向きを横断方向に正しく設定するためです。 - センターから5.0mと7.0mのポイントに幅杭を設置します。
- 一緒に幅杭の標高も測量(水準測量)します。
地盤高を計算しておくことで、これから紹介する計算方法により丁張の設置位置をおおよそ求めることができます。


丁張杭と横板を設置する
- 先ほど測量した幅杭の標高を基にして、おおよそ「切出し」となる近くに、「丁張杭」を0.3~0.4mほど離して2本打ち込みます。
- 2本の杭のうちどちらか1本の頭(天端)を水準測量して、標高を求めます。
- 丁張杭天端の標高が13.450mだったとすると、杭天端から0.450m下に横板を水平に取り付けます。
- 丁張横板の標高 H=13.450-0.450=13.000m とします。
- 0.450m下げた理由として、高低差の計算をなるべく簡単にすることによって計算ミスを少なくするためです。
ですので、丁張の「横板」から「FH掘削計画高さ」までの高低差を、区切りの良い数値になるよう0.100m単位で設定するのが良いでしょう。

- 丁張横板の上端(うわば)が計画高より高低差3.0mの位置に取り付けました。
- 掘削計画高が10.000m、丁張の横板の高さが13.000mで、高低差が3.000mです。

1:1.5(一割五分)の計算をする
高低差が3.000mの場合の水平距離を計算します。
法勾配が「1:1.5」の場合、「高低差の1.5倍」が水平距離となります。
したがって、
水平距離=3.000m×1.5=4.500m
となります。

センターから法尻(のりじり)まで、1.300m+0.500m=1.800m
したがって丁張高が13.000mの場合の「センター」から「切出し」までの水平距離はこうなります。
1.800m+4.500m=6.300m
高低差3.000mの場合、工作物及び作業スペースで1.800m、法面水平距離で4.500m、2つの距離を合わせると6.300mとなりました。
- 法尻とは、法面の下の部分です。
- 法肩とは、法面の上の部分です。

法丁張を掛ける
計算した結果、丁張高13.000mの場合、センターからの水平距離は「6.300m」なので、
センターから7.0mの幅杭から0.700mセンター側にスライドして
センターから6.300mの位置を丁張に印をします。

次に、印を基準に一割五分の板を取付けます。
1割5分は「スラント」で角度を合わせて、下の図のように板を打ち付けます。
丁張には「標高」・「センターからの距離」・「法勾配」・「法長」・「測点」などを記入し、目立つように着色しましょう。



最後に
法丁張は、「高低差」と「勾配」から「水平距離」を計算して、丁張を設置します。
法勾配は「高低差」が基準となっていますので、高低差に法勾配を掛算(×)して「水平距離」を求めましょう。
急傾斜地などに丁張を掛ける場合は、幅杭を多めに設置すると作業が楽になります。
以上となります。
現場測量の参考にしていだだけるとうれしいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
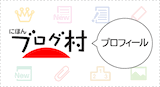
|
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |











