【トータルステーション】で水準測量「光波で高さを計算しよう」
このブログでは、「トータルステーション(T.S)」と「ターゲット(プリズム)」を使った「水準測量」の計算方法についてお話しします。
T.Sの測定結果で表示される「高低差」を使い、レベルと同じ「器高式」で標高(地盤高)を計算することが可能です。
T.Sの測定数値をそのまま器高式で計算するには、2つの条件があります。
- T.Sで測定した高低差の「符号(±)」を逆にする。
- 高低差測定時のターゲット高を変えないこと。

この2つの条件についてそれぞれ解説いたします。
距離を測る光波測距儀と、角度を測るセオドライトを組み合わせたもので、水平距離、高低差、斜距離、水平角度、鉛直角を表示することができます。

T.Sで測定した高低差の「符号(±)」を逆にする
T.Sの測定結果を器高式で計算する場合、T.Sより高い位置の値を「-」、低い位置の値を「+」というように符号を逆にする必要があります。

レベルを使った器高式の場合、測点は器械高より低い位置にあるという前提で測量結果を計算します。
つまり、器械高より低い測定値は「+」で計算するのが「器高式」ということになるからです。
図のように、左側の測点をB.Mとして、右側の測点を測量して標高を求めます。

上の図では、B.Sは「-3.416m」、F,Sは「2.542m」という測定結果です。
上の図の測定結果をもとに、「器高式」で地盤高を計算します。
最初に、測定した数値の符号を逆(+⇔ー)にします。
B.Sは「-3.416」→「+3.416」
F.Sは「2.542」→「-2.542」
| 測点 | B.S(バックサイト) | I.H(器械高) | F.S(フォアサイト) | G.H |
| BM(ベンチマーク) | +3.416 | 103.416 | 100.000 | |
| 測点(No,1) | -2.542 | 105.958 |
B.M(ベンチマーク)=100.000mとしています。
I.H(器械高)を計算します。
I.H=G.H+B.S
IH=100.000+(+3.416)=103.416m
測点№1を計算します。
測点№1:G.H=I.H-F.S
測点(№1)=103.416ー(-2.542)=105.958m
したがって、測点№1の地盤高GHは「105.958m」となりました。

「103.416-(-2.542)=105.958」のような、測定値にマイナス記号を付加した場合、計算上は二重のマイナスによってプラスに転換します。
ターゲットの高さを変えない
ターゲット高について
B.M(ベンチマーク)を測定した「ターゲット高」のまま、すべてのF.Sを測定します。
ターゲット高を変更する場合は、B.Mから測定するか、T.P(ターニングポイント)として新たに測定します。

ターゲット高を変えずに測定した場合、ターゲット高は相殺され、計算上ターゲット高を考慮する必要が無くなります。
間接水準測量とはいえ、ある程度正確な高低差を測量する場合は、B.Sと同じターゲットの高さでF.Sを測りましょう。

例えば、ターゲット高を「B.S=300㎜」、「F.S=500㎜」と変えて測定する場合、「ターゲット高」を正確に調整するのが難しいので、高さを変えずに測量する方が正確であり、計算によるミスも少なくなります。

ターゲット高は相殺される
ターゲット高が「相殺」されているのかを確認してみます。

先ほど計算した測点№1(GH=105.958m)と、ターゲット高を考慮した計算で求めた地盤高とで比較してみましょう。
ターゲット高をh=0.300mとして計算します。
先ほどの横断図の数値からターゲット高を引算します。
B.S=ー3.416ー0.300=ー3.716
F.S=+2.542ー0.300=+2.242


ターゲット高を引算した数値の符号を逆にします。「+」⇔「ー」
B.S=-3.716→+3.716
F.S=+2.242→-2.242
器高式で計算します。
| 測点 | B.S(バックサイト) | I.H(器械高) | F.S(フォアサイト) | G.H |
| BM(ベンチマーク) | +3.716 | 103.716 | 100.000 | |
| 測点(No,1) | -2.242 | 105.958 |
I.H(器械高)を計算します。
I.H=G.H+B.S
IH=100.000+(+3.716)=103.716
次に測りたいポイント№1を計算します。
測点№1:G.H=I.H-F.S
測点(№1)=103.716-(-2.242)=105.958
このように
ターゲット高を考慮して計算した結果 GH=105.958m
ターゲット高を考慮せず測定値をそのまま計算した結果GH=105.958m
ということで、同じ結果(地盤高)になり、相殺されていることが分かります。

このように、ターゲット高を変えないことによって、ターゲット高は相殺されることが分かります。
図で説明すると、平行にターゲットの高さ分だけ下がるだけで、高低差は変わりません。

実際の器械高は、「IH+ターゲット高」となります。
計算例
例として下のような断面図を用意しましたので、計算してみましょう。
T.Sで高低差を測定した数値は以下の通りです。

- ベンチマーク(BM)=100.000m、バックサイト(B.S)=+2.400m
- 測定1=+4.648m
- 測定2=+3.742m
- 測定3=+3.455m
- 測定4=-8.341m
- 測定5=-11.409m
- 測定6=-12.272m
- 測定7=-14.574m
測定した数値の符号を逆にします。「+」⇔「ー」
| 測点 | B.S(バックサイト) | I.H(器械高) | F.S(フォアサイト) | G.H |
| BM | -2.400 | 97.600 | 100.000 | |
| 測定1 | -4.648 | 102.248 | ||
| 測定2 | -3.742 | 101.342 | ||
| 測定3 | -3.455 | 101.055 | ||
| 測定4 | +8.341 | 89.259 | ||
| 測定5 | +11.409 | 86.191 | ||
| 測定6 | +12.272 | 85.328 | ||
| 測定7 | +14.574 | 83.026 | ||
IH=100.000+(-2.400)=97.600
測定1=97.600-(-4.648)=102.248
測定2=97.600-(-3.742)=101.342
測定3=97.600-(-3.455)=101.055
測定4=97.600-(+8.341)=89.259
測定5=97.600-(+11.409)=86.191
測定6=97.600-(+12.272)=85.328
測定7=97.600-(+14.574)=83.026

トータルステーションの誤差について
光波測距には大きく2つの誤差があります。
- 距離の大きさに比例して影響を与える誤差。
- 距離の大小に無関係な誤差です。
測定距離の精度の計算は、±(5㎜+5ppm×D)このような式があります。
ご使用されているトータルステーションの取扱説明書に記載されていますので確認してみてください。
詳しくは、こちらのブログでわかりやすく解説しておりますので、よかったら覗いてみてください。

T.Sでの水準測量は「間接水準測量」となります。
おわりに
今回のブログでは、トータルステーション(TS)をつかった水準測量の方法をお話ししました。
この測量のポイントとして、
- トータルステーションより高い位置の値を「-」、低い位置の値を「+」として通常通り器高式で計算する。
- ターゲットの高さを変えないこと。
- ターゲットの高さを変えないことによってターゲット高は相殺される。
以上になります。
皆様のスキルアップに役立てていただけたら幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。


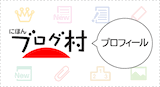
|
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |










