「平面図+横断図」を作成しよう【HO_CAD】

このブログでは、小規模の現況平面図と横断図を【TS(トータルステーション)】と【HO_CAD pao】を使って作成してみたいと思います。
今は「点群データ」や「BIM,CIM」のキーワードが目に付く時代なのですが、小規模現場の土量や簡単な地形測量にはトータルステーションで水平距離・水平角度・高低差を測定しています。
測量したデータを野帳(レベルブック)に記入しHO_CADの「測量」コマンドを使用して座標化(X,Y,Z)し、図面化(平面・横断)していきます。
今回はそのHO_CAD paoの「測量」コマンド使って、トータルステーションで測量した水平距離・水平角度・高低差を平面図と横断図にしていく方法についてわかりやすく解説します。
測量
例として、下の写真の赤い線で囲んだ場所にある土砂を撤去するのにおおよその土量を算出するために測量をします。

トータルステーションを使って放射状に「水平距離・水平角度・高低差」を計っていきます。
測定する前にターゲットを置く場所を予めスプレーなどでマーキングしておくと、TSを設置して、すべて見渡せることができるポイントを探せるのでおススメです。
横断図を作成することをイメージして、横断方向に測定する位置がくるようにマーキングします。
そして、平面図を作成することもイメージして、ターゲットをどの場所に置いたのかが分かるように、予め野帳に略図を書いておきましょう。

TSでの水準測量はターゲットの高さを最初に置いたポイントの高さのまま変えずに最後まで測量します。

ターゲットを変えずに測量する理由についてはこちらのブログ「トータルステーションで水準測量。光波で高さを測量しよう」で詳しく解説しております。

測量データ
現地の任意の点にトータルステーションを据付けて、先ほどマーキングしたポイントを測定します。
①のポイントを0セット(0度0分0秒)して、②~㉓までの水平距離・水平角度・高低差を全て測定しました。

高低差を計算して標高を求めよう(水準測量)
高低差のデータから現場内だけの標高を求めていきます。
①のポイントを、標高GH=10.000mとして、㉓までの標高を求めてみましょう。
標高の計算は、高低差の符号「+・-」を逆にして通常のレベルと同じ器高式で計算します。
+0.031は-0.031にします。
-0.545は+0.545です。
器械高IH=10.000+(-0.031)=9.969
②GH=9.969-(+0.545)=9.906
といったように計算していきます。

HO_CADの「測量」
CADの図面上に測量したデータを座標にして表示させたいと思います。
用紙の設定は「A3」
縮尺は「1/100」
TSから0セットした①のポイントまでの距離が13.439mなので、「線」と「複線」を使って画面に13.439を作ります。
座標系の設定
次に「測量」をクリックして、座標系を設定します。
上の「③座標系設定」をクリックします。

画面の線が交差している部分をTS器械点、上の線が交差している部分を0セットした①のポイントとします。
TSの器械点を座標系(0,0)とします。
下の図のように、線の交差部分を「右クリック」します。
XY座標が(0,0)で「OK」をクリックします。

器械点と0セットのポイントを座標へ変換
座標系を設定し終わったら、器械点と0セットした①のポイント13.439の2点の座標を図面上から拾います。
「測量」から上の「①測点編集(L)」をクリックします。

次に「①図面から拾う(R)」をクリックします。

下の図のように、線の交差部をそれぞれ「右クリック」して「OK」をクリックします。
画面上に座標ポイントが表示されます。
測点名を変えることもできますが、そのまま器械点を「pt-1」、0セットした①を「pt-2」としました。
「pt-2」の標高も「10.000」と入力します。


測量データを平面図へ
放射トラバース
②~㉓の測量したデータを入力します。
下の図のように「測量」の「⑦放射トラバース」をクリックします。

「器械点マウス指示」と表示されるので、「pt-1」を左クリックします。

次に、「後視点マウス指示」と表示されるので0セットした「pt-2」(①)をクリックします。

「放射トラバース計算」のウィンドウが表示されるので、②から㉓までのデータを入力します。
「測定水平角」の入力方法は、356度3分40秒を「356.0340」と入力します。
「測定距離」は水平距離をメートル単位で入力します。
「マーク」は画面上に表示されるポイントの形を15種類の中から選べます。
「サイズ」はマークの大きさを変えることができます。
「測点種別」は「なし・非表示・現況点・筆界点・図上点・引照点・基準点・図根点・多角点・幅杭」の中から選択できます。今回は現況点に設定します。
「標高桁」は「無・1桁・2桁・3桁」から選択できます。今回は3桁にします。

野帳の測量データを入力し終わったら、「計算開始」をクリックします。

画面上に座標に変換されたポイントが表示されます。
「計算結果を保存してよろしいですか」と表示されるので、「①保存」をクリックします。

標高の入力
次に標高を入力します。
画面左下の四角い部分「測点一覧表」をクリックします。
表示された表に、先ほど計算して野帳に記入した標高を下の図のように入力します。
入力し終わったら、「右上の「編集を適用」をクリックします。

画面には測点名と点だけが表示されているので、標高も表示させます。
標高にチェックマークを入れて「OK」をクリックします。

画面に標高が表示されます。


平面図の作成
野帳に書いた略図を参考に、点と点を線で結びます。

横断線と中央線(センター)を入れて平面図を仕上げます。
今まで作成した図面を複写して、別シートに貼り付けています。
CAD上で距離を測定します。
中央線に沿って横断線までの縦断距離と、中央線から横断方向に横断距離を測定して、画面に表示しました。
測点は、+0.00、+1.16、+8.71、+12.20、+18.57、+33.02、+36.57としました。

横断面図作成
平面図に表示してある「標高」と「横断距離」をもとに横断図を作りましょう。
+18.57の横断図を作図してみます。
測量した⑤⑥⑮⑲㉓の座標点をクリックすることで簡単に作図することができます。
コマンド「図形」から「⑥断面図作成」をクリックします。

「横断図作成」のダイヤログが表示されます。

距離:「絶対」は累計距離になります。
「点間」は単距離になります。
座標点をクリックする場合は「絶対」のままでおこないます。
高さは先ほど入力した値を使用するので「標高値」のままで行います。
横断図は左側から右側へプロットされていきます。
下の図のように座標点を右クリックしていきます。

クリックが終わったら「①作図実行」をクリックします。

プレビューに表示されている線形がマウスポインターについてくるので、画面上でクリックします。
「倍率指定」や「角度」で編集することができます。
貼付けが終わったら、「①次の断面図(L)」か「②断面図終了(R)」を選択します。

以上の操作を、すべての測点で行い、計画線や寸法を入れて編集すると下の図のようになります。

土量計算をしてみよう
各測点の断面積を図面から測定して、土量計算をします。
測点+18.57の赤くペイントした部分の断面積を測定してみましょう。
一番下にある「測定」をクリックして「②面積」をクリックします。

初期の設定が「㎜」単位なので、「m」単位で面積を表示しましょう。

横断図の各折れ点を赤い色を囲むように右クリックしていきます。

クリックが終わると「面積=37.64」と表示されます。
一覧表をクリックすると下の図のように表示されます。
これで面積の測定は終わりです。
この手順で、各横断図の断面積を測定していきます。

測定した断面積を「平均断面法」で土量計算(体積㎥)をExcelで計算します。
左から、測点と各横断面までの距離を入力します。
断面積は、先ほど横断図から測定した値を入力します。
平均断面積は、隣り合った測点の断面積を平均したものです。
土量は、平均断面積×単距離で計算します。
各測点の土量を合計して890.6m3という体積を計算することができます。




まとめ
このブログでは、トータルステーションで測量したデータを、HO_CAD paoで平面図と横断図を作成し、Excelで土量計算するところまでを解説しました。
この測量は、小規模な現場の大まかな土量を把握するのにおススメです。
手順は次の通りです
- トータルステーションで放射状に地形の変化点を水平距離・水平角度・高低差のデータを測定する。
- 高低差のデータを標高にする。
- HO_CADの「測量」コマンドを使用して、水平角度・水平距離を座標化する。
- 座標化した点を線で結び、平面図を作図する。
- コマンド「図形」から「横断図作成」をクリックして、座標点を右クリックで横断図を作図する。
- 作図した横断図に計画線を入れて各測点の断面積をHO_CADの「測定」を使い面積を求める。
- 求めた面積を、Excelを使用して平均断面法で土量を求めます。
以上になります。
このブログが皆様のお役に立てればとてもうれしいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
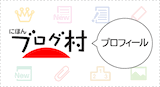
|
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |






