出来高払い方式を使った外注費の原価管理:Excel様式付き実践ガイド
建設現場では、外注先への支払いを「工事がすべて完了してから支払う」方式ではなく、進捗(出来高)に応じて支払う「出来高払い(出来高方式)」を採用するケースが多くあります。
しかし、この方式を導入すると「どこまでの作業分を支払うか」「支払額の根拠」「税務処理」「契約との整合性」など、現場と経理の両面で混乱が起こりやすくなります。
このブログでは、現場目線で「出来高払い外注管理」をExcelで実践する方法を、注意点も含めてわかりやすく解説します。実際に管理に使えるテンプレート(Excel様式)も想定しつつ、導入手順まで含めて紹介します。
Excelデータのダウンロード
月ごとの出来高払いを管理するためのExcel管理表をご用意しました。
参考にしていただければ幸いです。
以下のリンクからExcelデータをダウンロードできます。

出来高払いとは/方式の理解と導入要件
出来高払い方式とは、外注先が実際に完了させた作業分(出来形)に対して支払う方式です。
すべての工事を終えてから一括で支払うのではなく、段階的に精算する形になります。
この方式を採用するには、あらかじめ契約書で「出来高方式に基づく支払い条件」や査定基準、検収方法などを明文化しておく必要があります。建設業法の規定でも、契約段階で部分払(出来高払い)の定めを認めています。
また、出来高払いを正しく運用するには、以下のような実務的な前提が求められます:
- 出来形(進捗)を客観的に測る仕組み
- 検収(出来高検査)を確実に行える体制
- 支払タイミングの明確化(請求~支払までの期間)
- 契約条項と整合性を取ること
これらが整備されていないと、支払い根拠があいまいになり、トラブルの温床になります。
Excel原価管理「工事出来高管理調書」の使い方
Excelデータには「注文書内訳・出来高調書・出来高検収書」の3つのシートが含まれています。
Excelでの管理構成と各シートの役割
実際にExcelで出来高払いを運用する場合、以下のような構成を基本とすると現場で使いやすくなります。
| シート名 | 主な内容 | ポイント/注意点 |
|---|---|---|
| 注文内訳(工種・区分) | 各工事の契約金額、数量、仕様を列挙 | 契約時仕様と整合性を持たせ、改変履歴も残す |
| 出来高調書(査定記録) | 各期(例:月次)ごとの進捗率、実数量、出来高金額 | 査定基準、担当者記録、承認印などを残す |
| 出来高検収書 | 元請が検収した出来高を記録・承認する帳票 | 下請との相互確認、署名欄・添付図面を残す |
このようにシートを分けておくと、Excel上でも視認性が高まり管理ミスを減らせます。
注文内訳書
外注業者との取り決めた内容の内訳です。

出来高調書
月々の進捗状況が一覧表としてまとめられています。
例として、この契約では出来高に対して10%を「保留金」としています。
現場受取検査で問題が無ければ保留金を解除します。

上部の赤枠部分は、月ごとの出来高金額とその累計です。
同じく上部のオレンジ枠部分は、出来高金額から保留金を引いた額とその累計を表示しています。
表の左側(緑枠)は契約項目の内訳、右側(青枠)は出来高の内訳を示しています。
契約の進捗が一目で確認できるように工夫しています。
出来高検収書
出来高金額と保留金を除いた金額そして、消費税を含めた請求金額が分かりやすく表示されています。
この書類は、外注業者からの請求とともに提出してもらうことを想定しています。


実践的な運用ステップ
現場でExcel管理を始めるにあたって、以下のステップを目安に導入を進めましょう。
- 契約条項の確認と整備
出来高方式が明記されていない案件は、契約変更を含めて条項を追加しておく。査定方法・保留金割合・支払期日を明示。 - 初期導入シートの準備
上記のシート構成をベースに、自社/現場仕様に合わせて項目を調整する。 - 第1回出来高査定と検収記録
検収者が現場確認し、出来形をチェック。記録を「出来高検収書」に残す。 - 出来高金額の算定・請求処理
調書に基づいて金額を出し、請求書を作成。支払先とすり合わせ。 - 支払実績入力と残高チェック
支払後、支払一覧に記録。累計支払額と契約額との差異を監視。 - 改訂・追加対応
設計変更や追加工事が発生した場合、改訂項目を別枠で登録し、出来高調整を行う。
このような流れを定着させ、運用ルールを現場チームに共有しておくと、Excel管理でも運用しやすくなります。
税務処理・会計処理・留意点
出来高払い方式を採用する際、会計・税務処理における注意も不可欠です。
- 未成工事支出金
完成前に発生した原材料費・外注費などは、通常「未成工事支出金」勘定で処理され、工事完成時に「完成工事原価」として振替えます。 - 消費税(仕入税額控除)のタイミング
外注費については、原則として工事完成・引渡し時点で控除するのが基本ですが、元請業者が下請施工の出来高を検収し、「出来高検収書」が発行されている場合には、出来高分ごとに控除することが認められています。
ただし、人的役務のみを外注している場合などは、月次で控除できるケースもあります。 - 原価の不正防止・内部統制
出来高払いは査定の裁量が入るため、不正リスク(出来高の水増し、請求偽造など)が生じやすくなります。複数担当者のチェック、上席承認、定期的な別工事とのクロスチェックなどの内部統制が重要です。 - 建設業法上の支払遅延規制
発注者から受けた支払を下請業者へ還流する場合、支払い期間など法令遵守が求められます(例:下請への支払を不当に遅延させないよう義務付けられている)
導入上のヒント・注意点
- 工事件数や外注先が多くなるとExcelでは管理負荷が急激に上がります。そうした場合にはシステム化を検討することも視野に入れたほうが安定運用につながります。
- 出来高検収書・検収写真・現場写真の添付を徹底し、支払根拠の証拠を残すことが重要です。
- 出来高基準値(%基準や数量基準など)を契約段階で定め、後日の紛争を防ぐようにしましょう。
- Excelファイルには必ずバージョン管理を行い、誰がいつ修正したかのログを残しておくと、不整合時の原因追及が容易になります。
- 定期的に出来高調書と請求書・支払実績を突合させ、ズレがないか確認する習慣をつけておくと、未然にミスを防げます。
終わりに
出来高払い方式は、外注先との信頼関係を保ちつつ、工事進捗に即して公正に支払うための重要な方式です。ただし、導入には設計・契約・現場・経理の連携が不可欠であり、単にExcelを配るだけでは不完全になりがちです。
まずは本稿の構成をもとにテンプレートを作成し、ひとつの工事で運用してみてください。慣れてきたら他の現場にも展開し、必要に応じてシステム化を検討する流れが現場に即したステップです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
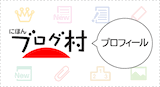
|
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |






