建設現場の【見積書】作成|提出までの流れ
まさあき
建設ナビ
このブログでは、土工事でおなじみの「土量の変化率」について解説します。
「土」には大きく分けて3つの状態があります。
自然な状態の土をほぐすと体積が増えて、締め固めると体積が小さくなります。
土量の変化率とは、地山の土量を「1.0」としたときの体積比で表したものをいいます。
地山土量を基準として、地山の変化率を「1.0」、ほぐした土量の変化率を「L」、締め固めた土量の変化率を「C」として表します。
L:ほぐし率(Loose)ルーズ
C:締固め率(Compact)コンパクト


ほぐし率Lと締固め率Cの値は、土質別に大きく変わります。
土量の変化率L=1.3、C=0.85とします。
地山土量200m3の運搬土量は?

1.3=運搬土量÷200
運搬土量= 200×1.3
= 260m3
地山土量200m3の盛土量は?

0.85=締固めた土量÷200
=200×0.85
=170m3
運搬土量1300m3の地山土量は?

1.3=1300÷地山土量
地山土量=1300÷1.3
=1000m3
盛土量3000m3の運搬土量は?

0.85=3000÷地山土量
地山土量=3000÷0.85
=3529m3
1.3=ほぐした土量÷3529
ほぐした土量=3529×1.3
=4588m3

計算結果はこちらです

今回のブログでは、「土量の変化率」について解説させていただきました。
土は「ほぐす」と地山より体積が多くなり、「締固める」と地山より体積が少なくなります。
変化率の関係は次の式になります。

L:ほぐし率(Loose)ルーズ
C:締固め率(Compact)コンパクト
最後までお読みいただきありがとうございました。
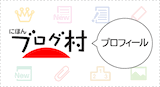
|
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |