【現場密度試験】の計算方法を分かりやすく解説「様式(KODAN A1214)ダウンロード付」

このブログでは、現場密度試験の計算方法についてお話しします。
様式「KODAN A1214」を使い、実際に数値を入力して1つ1つ解説いたします。
試験方法についてはこちらのブログを参考にしてください。

様式「KODAN A1214」
例として路床盛土を施工した場合を想定しました。
様式のダウンロードはこちらから ↓↓↓↓

事前準備
試験前の準備を行い、事前に記入します。

⑤「砂(試験用砂)の単位体積重量」をキャリブレーション容器で行い、例として「1.576」と記入します。
キャリブレーション容器に砂を入れた状態の重さからキャリブレーション容器の重さを引き算して、キャリブレーション容器の体積で割り算します。

⑧「容器重量」として、使用するビニール袋の重さを計ります。「14」と記入します。
①「試験前(砂+容器)重量」試験孔に入れる前の砂+容器の重さを計ります。今回は計算しやすいように「5000」と記入します。
③「ベースプレート中の砂の重量」を算出して「278」と記入します。
ベースプレートの直径が15㎝に厚さが1㎝の体積に、単位体積重量を掛け算します。

⑲「最大乾燥密度」を盛土材の試験成績表から「1.836」と記入します。
以上で、事前準備は完了です。

現場試験
次は実際に現場で試験を行い、記入しながら計算をします。
最初に試験箇所にベースプレートを置き、試験孔を掘ります。
試験孔から掘り出した試料をビニール袋に入れて重さを計ります。

⑦「(湿潤土+容器)重量」掘り出した試料の重さを計ります。「3625」と記入して、⑨を計算します。
⑨「湿潤土重量」=( ⑦ ー ⑧ )=3625ー14=3611 ⑦からビニール袋の重さを引き算します。

ベースプレートに上枠を設置して、試験孔に試験用砂を入れます。
突き棒で所定の回数を突き、余分な砂を戻します。

②「試験後(砂+容器)重量」を計り、「1921」と記入します。
④と⑥と⑩を計算します。
④「穴につめた砂の重量①ー(②+③))」=5000ー(1921+278)=2801
⑥「穴の容積(④/⑤)」=2801÷1.576=1777
⑩「湿潤密度(⑨/⑥)」=3611÷1777=2.032 となります。

推定含水比から推定締固め度
推定含水比から推定締固め度を出してみましょう。
現地でおおよその結果が出せるので、段階確認や立会検査でとても有効です。
推定含水比を、例えば12.0%として⑬乾燥土重量と⑭乾燥密度を逆算します。
⑬「乾燥土重量(推定)」={⑨÷(12.0+100)}×100
=(3611÷112)×100=3224
⑭「乾燥密度(推定)」=⑬/⑥=3224÷1777=1.814
したがって推定締固め度は
締固め度(推定)=100×⑭/⑲=1.814÷1.836=98.8%
となります。
含水比試験を行い正確な締固め度を求める
試験孔から掘り出した試料は、持ち帰り「含水比試験」をします。
含水比試験には「炉乾燥法」と「電子レンジ法」そして「フライパン法」があります。
含水比試験から「含水比」を求めて、「締固め度」を算出します。
含水比試験
⑪~⑯で含水比を求めます。

⑪は試験孔から掘り出した試料を乾燥させた「乾燥土+容器」の重さです。
⑪=3451
⑫は「容器」の重さです。⑫=210
⑬「乾燥土重量」⑪ー⑫=3451-210=3241
⑭「乾燥密度」=⑬/⑥=3241÷1777=1.824
⑮「水の重量」=⑨ー⑬=3611ー3241=370
⑯「含水比」=100×⑮/⑬=100×370÷3241=11.4
となります。
締固め度

締固め度は、先ほど求めた⑭「乾燥密度」と盛土材の試験成績表の「最大乾燥密度」の割合です。
Dc=100×⑭/⑲=100×1.824÷1.836=99.3%
締固め度は「99.3%」となります。
礫補正
室内試験は粒径37.5㎜以下の試料を行っているので、粒径37.5㎜以上の礫が混入している場合、最大乾燥密度を補正する必要があります。
例として計算してみます
⑰「礫の乾燥重量」=420
「礫の積比重」=2.20
⑱「混礫率P」=(100×⑰/⑬)=(100×420÷3241)=13.0%
⑳「最大乾燥密度の補正値」γdo=1/((1-P)/⑲)+(P/水の比重×礫の積比重))
=1÷((1-0.13÷1.836)+(0.13÷1×2.20)=1.890
となり、礫が混入した場合の最大乾燥密度=1.890
礫が混入した場合の締固め度 Dc=100×⑭/⑳=100×1.824÷1.890=96.5%
となります。
おわりに
現場密度試験【突砂法】の計算方法を、具体的な数値を例にして解説しました。
- 現場へ行く前の「事前準備」を行い、数値を記入します。
- 現場で試験を実際に行い、試験孔を掘り試料を採取します。
- 推定含水比で乾燥密度を逆算して、推定締固め度を求めます。段階確認・立会の時に使います。
- 試験孔から掘り出した試料を持ち帰り含水比試験を行います。
- 含水比を算出して、締固め度を求めます。
- 粒径37.5㎜以上の礫が混入している場合、最大乾燥密度を補正して締固め度を求めます。
以上、現場密度試験突き砂法の計算方法でした。
このブログが皆様のお役に立てたら嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。

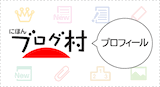
|
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |







