【法丁張】の計算方法|盛土法面1:1.5丁張の作り方
建設現場の「盛土法面丁張」を作る為の方計算方法について解説します。

法面丁張を作るうえでのポイントは次の通りです。
高低差×法勾配=水平距離
今回解説する建設現場の設定は、下の横断図のように盛土高「1.0m」、盛土法面勾配「1:1.5」としています。
現地には「法肩」となる位置を真直ぐ下におろした「法肩杭」が設置されています。
この「法肩杭」を基準に法面丁張を作るという設定です。

スラントを使わない法面丁張の掛け方を解説しますね。

法尻位置の計算
盛土の外側に2本の杭を立てるために、「法尻」となる位置を計算します。
地盤をレベルで水準測量し、標高(地盤高)を計算します。
地盤高が13.00m(おおよそで大丈夫です)
盛土計画高が14.000mとなるので、高低差が「1.0m」になります。
高低差に法勾配の「1.5」を掛算して水平距離を計算します。
1.0m×1.5=1.5m(水平距離)

ということで、「法肩杭」から1.5mの位置が「法尻」となります。
下の図のように、法尻となる位置から盛土の中に入らない位置に杭を2本打ち込みます。

水平貫(横の板)を取付ける
杭を2本打ち終わったら、杭の天端をレベルで水準測量します。
測量した杭の上を基準に、2枚の板を水平に取り付けます。
下の板の標高をH=13.200m
上の板の標高をH=13.500m
としました。
計算しやすいように盛土法肩計画高までの高低差が10cm単位になるように板を取付けるのがポイントとなります。
板の上面か下面に高低差の位置を合わせます。

法面丁張は上面(上端)のほうが作りやすいですね。

法面の位置をマーキングする
取り付けた2枚の水平貫(横の板)に、法面1:1.5の位置を印します。

最初に下の水平貫から法面位置の印をしてみましょう。
高低差H=14.000-13.200=0.800m
法肩杭からの水平距離L=0.800m×1.5=1.200m
となります。


次に上の水平貫(横の板)に法面の位置を印しましょう。
1枚目に印をした位置を垂直に上げます。
1枚目と2枚目の板の高低差は0.30mですので、
下の板からの水平距離=0.30m×1.5=0.450m
となります。

法面勾配の板を取り付ける
2枚の水平貫に法面勾配の印をつけたら、印と印を結んで法面勾配の板を取付けます。
盛土の中に入ってしまう水平貫を切り落としましょう。
スラントで法勾配を確認します。

盛土法面丁張完成
法面丁張に「測点・法長・法勾配・水平貫の標高・センター杭からの離れなど」を記入して完了となります。

1:1.5法面勾配は、高低差「1」に対して水平距離が「1.5」というように高低差が基準となっております。
法面勾配についてはこちらのブログで詳しく解説しております。
良かったら参考にしてください。


今回のブログは以上となります。

最後までお読みいただきありがとうございました。
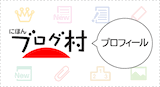
|
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |







